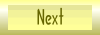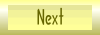
|
私の小学生の頃までは石積みの「かまど」、「ひちりん」、「火鉢」であぶりもので魚を焼いて 蒔きを燃やし、ご飯、煮物を炊き、暖房は「炭」、「練炭」、「炬燵」、「火鉢」であったが、現代 は「ブロパンガス」、「電化」された機器に変わった。時代ですね〜 これを進歩と言うのか ? いざ、災害で電気の供給が止まると昔の「蒔き」、「炭」、「ろうそく」のお世話にならざるを得 ないのである。 この師走の時期、「餅つき屋」と言って台八車に簡易の「かまど」で何段にも重ねた「せいろ」 で餅米を蒸し、臼、杵、で「餅」を附く。屈強そうな「叔父さん」が捻り鉢巻をし、つき手と返し のコンビは絶妙で、たちまち一臼(二升)、二臼と鏡餅や、附きたての餅に大根おろし、納豆、 あんこ、黄な粉と、それはそれは「うまかった」と記憶に残っている。 こんな風景は今は昔と笑うが、衛生法かなんやかんやで、出来なくなったそうな〜 懐かしいですね〜 思い出しましたよ。 |