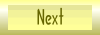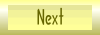
|
鰤さん達よ、団体で南下の途中、ようこそ富山湾へ、毎年ご苦労さん。 ここで「鰤」についてのルーツを調べると、正式学名は「ススキ目アジ科 ブリ属」とある。 戸籍は3月〜5月に九州付近で誕生。1尾で一年に約300万粒の卵を 生み「モジャコ」として稚魚になり、流れ藻に付着しエサを捕りながら 成長。但しその生存率はわずか、0.1%、3000尾と言われている。 春〜夏にかけて日本海を北上し、晩秋から初冬にかけて南下を毎年繰り 返す。 寿命は最長7〜8年、体長1.5m位に体重13〜15Kgになる。 モジャコ(当歳魚)⇒ツバイソ⇒コズライ⇒フクラギ⇒そしてガンド(1歳 魚)⇒二マイズル(2歳魚)⇒ブリ(3歳魚)へと成長、それからサンカブリ (4歳魚)⇒オオブリ(5歳魚)と呼ばれる。 さて、その回遊の習性を知った人間は、多分、大昔は一本釣だったと 思われますが、江戸時代頃から九州辺りで敷き網での捕獲が考案され、 この時期に大量に捕るようになった。 この富山湾の沿岸でも、大敷き網の漁法が盛んで、沖合いに向かって 何キロもの網をカ―テンのように張り、鰤が網を伝って逃げ口を探して いる内に袋の中に入ってしまう大仕掛けの漁が県東部8枚、県中部37枚、 県西部34枚張り巡らされている。これではやはり逃げ場が無いと言って いいでしょうが、ここが『鰤と人間の知恵比べ』。 私は以前から鰤に進化論を説いてきた。太古の昔からの回遊のルートを 修正し生き残りを考えよと! 動物の進化は、長い長いスパンで見なくてはと思いつつも「もう〜いい だろう革命を起こせ」と!! 漁師の人に叱られそうだね〜。しかし、江戸時代から富山の鰤は『正月』 には欠かせない魚として食卓に上がり、『出世魚』として祝い事にも用い られ重宝がられている。 また、海の無い岐阜、神岡、高山、遠くは松本、長野まで加工された 『寒鰤』『塩鰤』として牛車で、又は歩苛で運ばれ、『冬の海の王者』と しての貫禄は今も健在で威厳あり・・・ 従って「鰤達よ」今日も県内の漁港では、仲間達、数千本が水揚げされ ているぞ〜。生まれ故郷の九州へ何本の仲間が辿り着くのやら・・・ そして、また来年も歴史は繰り返えされるのか 一回遊、1CMつづでもと願いつつ・・・ |